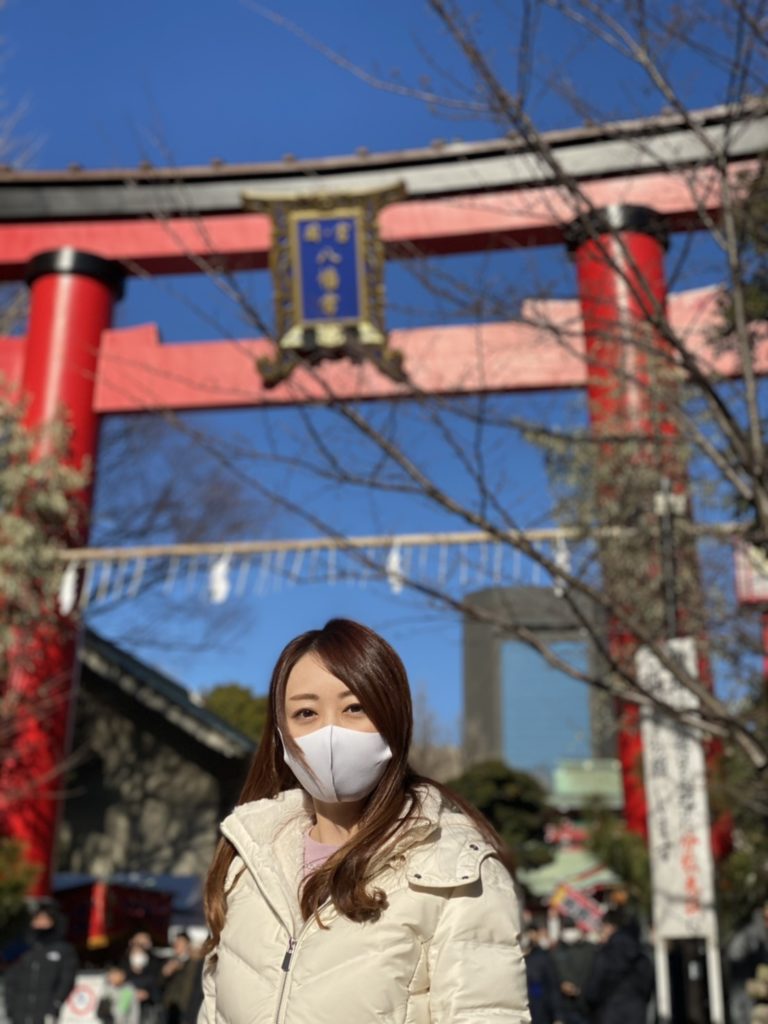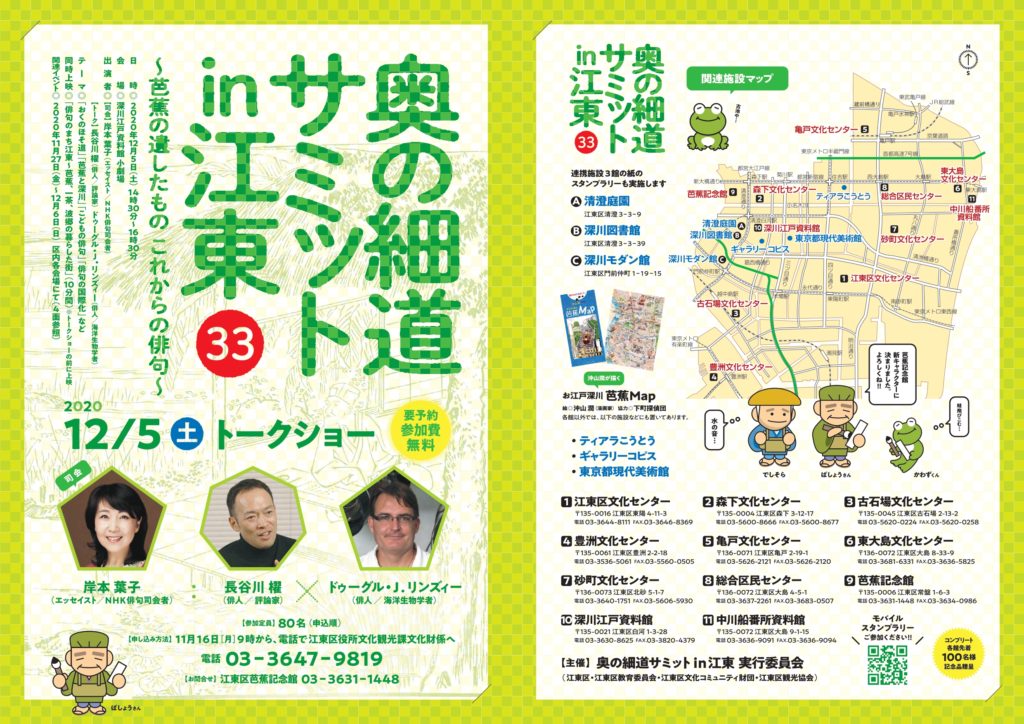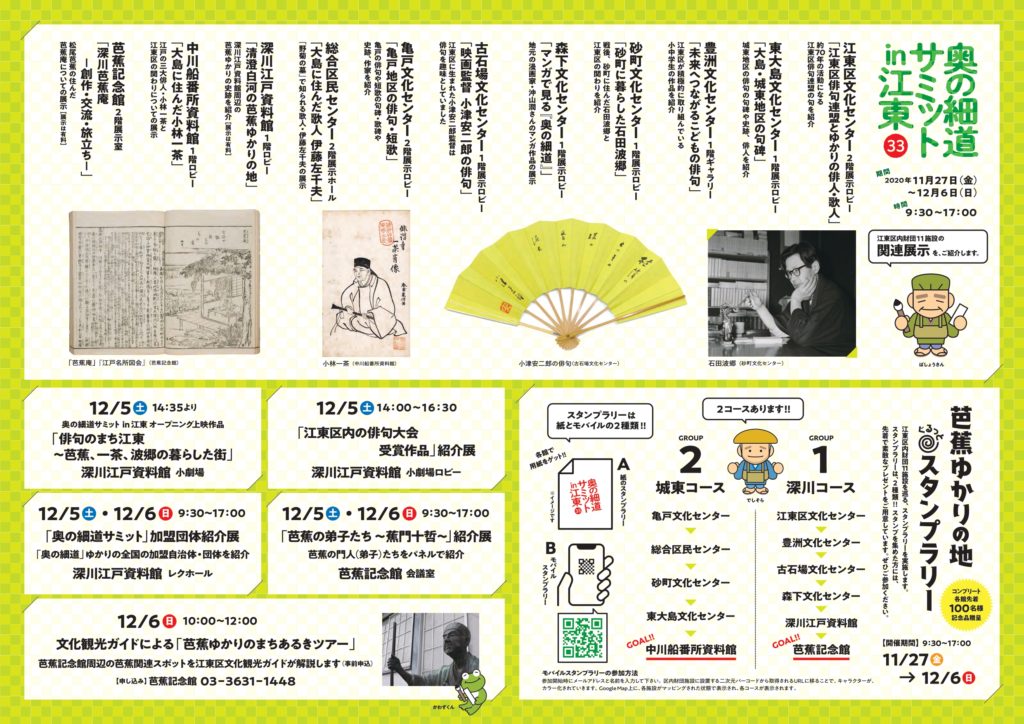「暑い、溶けそう。」と道行く学生たちの会話が聞こえる。
クーラーの効いた部屋から一歩出た瞬間に汗がにじむのが分かる。
公園で走りまわる子ども達の姿は消えてしまった。
米国では最高気温が50度を超える地域もあり、熱中症関連の死亡が増加。
地面に転んだだけで生命を脅かすほどの重いやけどを負う人が出ている。
地中海沿岸の国では猛暑による山火事のために40人以上が命を落とし、アジアでも熱波による死者が増えて食糧の安全が脅かされている。
つまり、今年の暑さは異常である。
「暑すぎて死ぬ」が冗談じゃなくなる時代になってしまうのだろうか。
*
米国立環境予測センターの観測データの分析から、7月4日の地球全体の平均気温(世界平均気温)は17.18℃で、1979年の衛星観測開始以来、最も暑い日であったことが分かりました。米ワシントン・ポスト紙によると、「過去12万5000年間の地球史上で、最高気温と考えられる」と指摘する気象学者もいると言います。
今年の地球規模の猛暑は、何が原因なのでしょうか。
世界では19~20世紀にかけて国立の気象観測機関を発足させて、自国の気象データを精密に計測し、公表するようになりました。
今回の「世界平均気温の最高記録達成」は、米国立環境予測センターが衛星データを含めて全地球の観測を記録し始めた1979年以降で最高気温となっています。
気象観測は自然現象を書き留めたり、季節ごとの変化を参考にしたりすることは、農業や防災、健康管理に必要不可欠な作業でした。
近代的な気象観測は、地上、海洋、高層大気、衛星データによって行われています。また、地上気象観測は最も古くから行われてきており、天気、気温、気圧、降水量、湿度、風向風速、日射量などのデータは、長年の蓄積があります。
*
では、過去12万年間で過去最高気温である根拠とは何なのでしょうか。
研究者らは、北半球が夏季であることに加えて、
・気候変動(氷期と間氷期の長期サイクル・人類の活動によって温室効果ガスの排出が進んだという意味合いを含む。)
・エルニーニョの発生
によって、地球の最高気温が更新されたと言っています。
今回も、地層やサンゴ、アイスコア類に保存されている数十万年分の気泡やちりなどの分析から、「世界の平均気温はおよそ12万年ぶりの最高気温を記録」と報じました。
また今年のエルニーニョの発生は世界中でされており、日本の気象庁も6月9日、4年ぶりにエルニーニョが発生したと発表しています。
※エルニーニョ現象とは:太平洋赤道域の日付変更線付近から南米沿岸にかけて海面水温が平年よりも高くなり、その状態が1年程度続く現象。エルニーニョが発生すると、世界中の気象に影響を及ぼし、地域によって干ばつや豪雨など様々な異常気象を引き起こし、地球全体では記録的な猛暑になりやすいと言われています。
*
今回の「地球史上、最も暑い日」の記録を受けて、専門家たちは「温室効果ガスの排出量抑制に迅速に取り組まないと、今後も最高気温が塗り替え続けられるだろう」と警告しています。
一方、人類の発展に伴って急ペースで温室効果ガスが増えたことについて、悪いことばかりではないと考える人たちもいます。たとえば、多くの植物の発育適温は、現在の平均温度よりもやや高いとするデータがあります。
独ポツダム気候影響研究所の研究チームは、「人類が大気に排出してきた温室効果ガスによって、次の氷河期の開始が5万年以上後ろ倒しになったかもしれない」とする論文を、16年に科学総合誌「ネイチャー」に発表しました。
同研究所のアンドレイ・ガノポルスキ博士は「地球の公転軌道などから算出すると、本来は200年前に氷河期に突入するはずだった。当時、大気中の二酸化炭素濃度が240ppmだったならば氷河期は開始したかもしれないが、産業革命以前でも人類が森林伐採をしたことなどによって280ppmになっていた」と説明します。英ユニバーシティー・カレッジ・ロンドンのクリス・ラプリー教授は、この研究成果を受けて「人類の行動が惑星の新陳代謝そのものを左右する、新しい時代に入った証拠だ」と語っています。
*
さて、ここで私たちは「自然には抗えない・自然災害は仕方ない」で傍観していて良いのでしょうか。
国連広報センターのホームページでは、気候変動に対して、個人でできる10の対策が挙げられています。
1.家庭で節電する
2.徒歩や自転車で移動する、または公共交通機関を利用する
3.野菜をもっと多く食べる
4.長距離の移動手段を考える
5.廃棄食品を減らす
6.リデュース、リユース、リペア、リサイクル
7.家庭のエネルギー源を変える
8.電気自動車に乗り換える
9.環境に配慮した商品を選ぶ
10.声を上げる
気候変動は大きな問題ですが、こうしてみると今からでも取り組めることがありそうですね。私たち一人ひとりがこの問題に向き合っていかなくてはなりません。
*
↓金澤ゆいを応援する
https://kanazawayui.com/donation/